「営業代行はやめとけ」と言われる本当の理由と成功する活用法
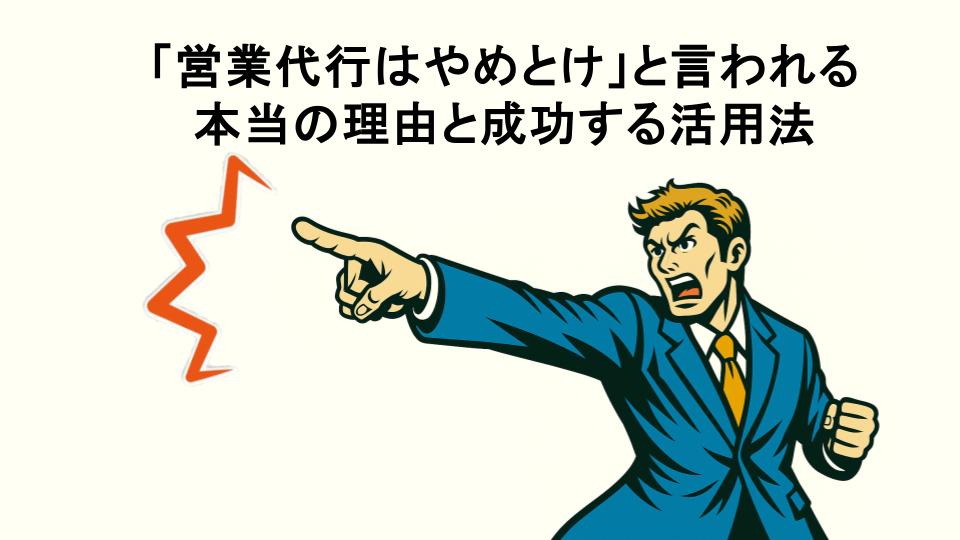
「営業代行はやめとけ」と言われる本当の理由と成功する活用法
「営業代行はやめとけ」と聞いたことはありませんか?実は、営業代行を正しく活用できていない企業ほど、そのような失敗を経験しています。本記事では、営業代行が「やめとけ」と言われる理由をはじめ、営業代行・フリーランス・自社営業の違い、代行業者の選び方、成功事例、内製化への移行ステップまでを徹底解説。これから営業代行を導入すべきかどうか迷っている方、自社に最適な営業戦略を見直したい方に向けて、実用的な情報を網羅しています。
この記事を読むと、以下のことが分かります。
- 営業代行が「やめとけ」と言われる理由と、失敗を防ぐ具体的な対策
- フリーランス営業・自社営業との違いと、自社に合った営業手段の見極め方
- 成功している東京企業の営業代行活用事例とその共通点
- 営業代行導入から内製化までのステップと、継続的な営業力の育て方
はじめに
この記事の目的と対象読者
営業代行というサービスは、営業リソース不足や新規開拓の課題を抱える企業にとって、魅力的なソリューションとして知られています。しかしその一方で、「営業代行はやめとけ」「効果がない」「トラブルになった」という声も多く見受けられます。
本記事は、そうしたネガティブな評判の真相を明らかにしつつ、「なぜやめた方がいいのか」「どのように選べば成功するのか」「営業代行以外にどのような選択肢があるのか」など、営業代行を検討しているすべての方にとって判断材料となる情報を提供することを目的としています。
特に以下のような方には、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。
- 東京で営業代行を検討している中小企業の経営者・営業責任者
- 以前に営業代行で失敗した経験がある方
- 自社営業と外部委託、どちらが効果的か悩んでいる方
- 営業活動におけるコストと成果のバランスに課題を感じている方
この記事を通じて、営業代行の本質的なメリット・デメリットを整理し、自社にとって最適な営業体制を構築するヒントを得ていただければ幸いです。
「営業代行 やめとけ」と検索される背景とは?
「営業代行 やめとけ」というキーワードがGoogleで頻繁に検索されている背景には、いくつかの共通した不安や疑念があります。実際に検索結果の上位には、「営業代行で失敗した事例」や「費用対効果が合わなかった理由」「ブラックな代行業者に注意」といったネガティブな情報が並んでいます。
営業代行を検討する企業が増えている一方で、その実態や仕組みを正しく理解せずに導入してしまうケースが多く、その結果「期待した成果が得られない」「営業活動が不透明だった」「高額な費用だけが残った」といった声が上がっているのです。
本記事では、これらの不安を一つひとつ丁寧に検証し、誤解なのか事実なのか、そしてどのように対応すべきかを具体的に解説していきます。
営業代行はやめとけと言われる6つの理由
営業代行に対する不信感が生まれるのには、明確な理由があります。以下では、多くの企業が営業代行の利用を躊躇する、または利用後に後悔する主な6つの原因を詳しくご紹介します。
成果が出ない・費用対効果が悪い
営業代行を導入して最も多い不満が、「思ったより成果が出ない」という点です。営業代行はあくまで外部リソースですので、自社のサービスや商材を深く理解し、的確にアプローチできるようになるまでに時間がかかります。
特に、成果報酬型の契約にした場合、「成果が出るまでは費用がかからない」という安心感からスタートするものの、成果が出ずに終わってしまう、あるいは成果が出ても契約数が少なく、コストに見合わないと感じるケースが後を絶ちません。
また、固定報酬型を採用した場合は、「成果がゼロでも毎月支払わなければならない」といった不公平感を抱くことも。そもそも、商材の難易度や市場ニーズと営業代行会社のスキルがミスマッチであると、どれだけアプローチを重ねても効果が出にくいのです。
そのため、営業代行に成果を求めるのであれば、費用対効果を事前にシミュレーションし、契約期間中に得られるであろう成果の基準を明確にしておくことが不可欠です。
営業活動が見えづらく、ブラックボックス化
営業代行のもう一つの大きな課題は、「実際に何をしているのか分からない」という点です。
たとえば、テレアポやメールマーケティングなどのアウトバウンド施策を委託した際、どのリストにどんなアプローチをしたのか、反応はどうだったのか、営業プロセスはどう設計されているのか、といった情報が企業側に共有されないことが少なくありません。
このように営業活動がブラックボックス化してしまうと、PDCAを回すことも難しく、改善もできません。また、営業代行側が最も効率的と判断した方法が、必ずしも自社のブランディングや方針と合致しているとは限らないため、マーケティング戦略全体との整合性が崩れるリスクもあります。
その結果、「何をやっていたのか分からないまま、時間とお金だけが浪費された」という事態にもなりかねません。
自社にノウハウが蓄積されない
営業代行を利用する最大のデメリットのひとつが、「営業ノウハウが社内に蓄積されにくい」という点です。営業活動を完全に外部に委託してしまうと、商談のプロセスや顧客とのやり取りの中で得られる気づき、トーク内容、競合状況といった生きた情報が社内に共有されにくくなります。
とくにBtoB商材のように、顧客の課題や業界動向を深く理解する必要があるケースでは、営業活動を通じた学びこそが今後のプロダクト改善やマーケティング戦略に大きく影響します。ところが、営業代行に丸投げをしてしまうと、そうした情報は外部に留まり、自社内には何も残らない状態になってしまいます。
将来的に内製の営業体制を構築したい、若手の育成をしたいと考えている企業にとっては、この点は大きな機会損失となります。営業代行に頼ることで一時的な成果を得たとしても、会社としての営業力が成長しなければ、長期的には限界がくるのです。
強引な営業で評判が悪化するリスク
営業代行会社によっては、成果を出すことを最優先し、顧客の状況を考慮せずに強引な営業を行うケースもあります。これは特に成果報酬型の契約にありがちで、「アポ数を増やすためだけの営業」が横行してしまい、企業のイメージダウンにつながる危険性があります。
例えば、断られているにも関わらず何度も電話をかけ続けたり、相手の業種やニーズを把握しないままアプローチを行ったりといった対応は、ターゲット企業からのクレームに発展する可能性があります。
実際に、「営業代行会社の対応が悪く、御社とは取引したくないと言われた」という報告もあります。これは企業ブランドにとって致命的であり、長年かけて築いてきた信用を一瞬で失うリスクでもあります。
営業活動とは、単なる数ではなく、顧客との信頼関係構築が大前提です。代行会社の営業スタイルが自社の企業文化や理念と一致していない場合、大きな損失を被ることになりかねません。
情報漏洩やデータ管理の不安
営業代行を利用する際、顧客リストや取引先の情報など、重要な営業データを外部に共有する必要があります。これは営業代行の性質上避けられないことですが、その分情報漏洩リスクを常に抱えることになります。
信頼できる営業代行会社であれば、契約書で秘密保持条項(NDA)を締結し、社内の情報セキュリティ体制もしっかり整備されているでしょう。しかし、すべての会社が万全な体制を取っているとは限りません。
悪質な業者の場合、取得した顧客リストを他社に流用したり、営業活動のログや録音データを適切に管理せずに放置したりといったケースも存在します。
特に東京のような大都市圏では競争も激しく、営業リストの価値が高いため、情報の取り扱いには細心の注意が必要です。万が一でも顧客情報が漏洩すれば、信頼の失墜だけでなく、訴訟や損害賠償といった事態にも発展しかねません。
商材とのミスマッチで機会損失が起きる
営業代行は、あらゆる商材に対して万能というわけではありません。たとえば、高度な専門知識が必要なITシステム、医療機器、不動産、士業系のコンサルティングサービスなどは、営業代行のスタッフが内容を理解できなければ適切に営業活動を行うことはできません。
このような場合、せっかく営業をかけても商談につながらなかったり、顧客との会話がかみ合わずに信頼を失ったりといった結果になりがちです。また、商材の強みや訴求ポイントを伝えきれないまま、ただの価格勝負になってしまう可能性もあります。
営業代行会社によっては「どんな商材でも営業可能」と謳っているところもありますが、実際には得意・不得意の分野があるものです。しっかりと自社の商品やサービスに合った代行業者を選定しなければ、成果を出すどころか機会損失を招くことになります。
営業代行・フリーランス・自社営業の比較<
営業代行の特徴と限界
営業代行は、自社の営業活動を外部の専門会社に委託する形態であり、主に新規顧客開拓やアポイント獲得を目的としています。東京などの都市部では特にニーズが高く、スタートアップ企業や営業リソースに課題を抱える中小企業を中心に活用が広がっています。
営業代行の最大の魅力は、即戦力の営業マンを外部から確保できることにあります。自社で人材を採用・育成する時間とコストを抑えつつ、一定の成果を短期間で得られる可能性があります。
一方で限界も明確です。先ほど述べたように、商材に対する理解が浅いと成果が出にくく、またコミュニケーションや情報共有が不足していると戦略の整合性が損なわれます。さらに、営業活動のすべてを丸投げしてしまうと、自社の営業力は育たず、依存体質になってしまう恐れもあるのです。
フリーランス営業の柔軟性と専門性
近年では、営業代行の代替手段として「フリーランス営業」を活用する企業も増えています。特に東京を中心に、特定分野に強い営業のプロがフリーで活動しているケースが多く見られます。
フリーランス営業の強みは、専門性と柔軟性にあります。IT業界に特化したフリーランス、医療業界の営業経験が豊富なフリーランスなど、自社の商材や業界に精通した人材をピンポイントで採用することができます。また、業務委託契約のため、必要な期間だけ、必要な成果に応じて報酬を支払うことが可能です。
ただし、個人であるがゆえのリスクもあります。例えば、急な契約解除、対応スピードの遅れ、情報管理の不備などが発生する可能性もあるため、業務内容や責任範囲を明確にした契約書の締結が重要です。
内製営業のメリットと成長機会
営業手段の中で最も長期的な成長が期待できるのが、自社で営業部隊を構築する「内製営業」です。自社の製品・サービスを深く理解している社員が営業活動を行うことで、より的確な提案ができ、顧客との信頼関係も築きやすくなります。
また、営業活動の中で得られた顧客の声を、商品改善やマーケティング戦略にフィードバックできるため、企業全体の成長にもつながります。社員に営業スキルを定着させ、ノウハウを社内に蓄積することで、組織としての営業力が着実に高まっていきます。
もちろん、内製化には人件費や教育コストがかかります。立ち上げ当初は成果が出るまでに時間がかかることもあります。しかし長期的な視点で見ると、自社の中に営業という機能を根付かせることは、極めて大きな資産になるのです。
営業代行を活用する3つのメリット
営業代行にはリスクもありますが、適切に活用することで多くのメリットを享受することができます。ここでは特に代表的な3つのメリットについて解説します。
営業リソースの即時確保
営業代行を活用する最大の利点は、即戦力となる営業人材をスピーディーに確保できる点です。採用活動や研修の手間がかからず、すぐに営業活動をスタートできるため、「すぐにでも営業を強化したい」というニーズに対応できます。
特に東京のような競争の激しい市場では、新規開拓のスピードが成果を左右する場面が多々あります。営業代行を使えば、短期間で複数の案件を並行して進めることが可能になり、営業機会の損失を防ぐことができます。
新規顧客開拓のスピードアップ
営業代行会社は、豊富な営業リストやターゲット選定ノウハウを持っています。特定の業界や地域に強い営業代行会社であれば、効率よくアプローチ先を抽出し、短期間で成果を出すことも可能です。
自社でゼロからリードを集めるには時間がかかりますが、営業代行を活用すれば、その時間を大幅に短縮できます。とくに新サービスのローンチ時や、新市場に進出したいときなど、「スピード」が最優先される場面では大きな武器となります。
社内リソースの最適化と集中
営業代行を活用することで、社内の人材やリソースをコア業務に集中させることができます。たとえば、マーケティングや商品開発、既存顧客のフォローアップといった業務にリソースを回すことで、会社全体の生産性を向上させることができます。
また、営業活動を外部に委託することで、社員が本来注力すべき分野に専念できるようになるのも大きなメリットです。営業代行との分業体制を上手く構築することで、社内外の連携が生まれ、結果的に組織の総合力を高めることにもつながります。
営業代行が向いている企業・向いていない企業
営業経験・リソースが不足している企業
営業代行は、営業体制が十分に整っていない企業にとって非常に有効な手段です。特に、スタートアップ企業や中小企業、営業専門の人材が社内にいない企業にとっては、営業代行の活用によって即戦力を得ることができます。
たとえば、事業立ち上げ期や新しいサービスのリリースタイミングでは、限られた人員で全方位の営業活動を行うのは難しいものです。こうした状況で営業代行を活用すれば、スピード感を持って新規顧客の獲得を進めることができるため、大きな武器になります。
また、営業活動にかかる人的・時間的コストを外部に任せることで、社内の限られた人材をマーケティングや製品開発、顧客対応といったコア業務に集中させることも可能になります。
高い専門性やブランド統一が必要な企業
一方で、営業代行が向いていない企業も存在します。それは、取り扱う商材に高度な専門知識や業界特有の経験が必要な場合や、自社ブランドや顧客との信頼関係を極めて重要視する場合です。
たとえば、医療機器、先進的なITソリューション、法律・会計・税務などの士業サービスなどが該当します。これらの業界では、単に商品の特徴を説明するだけではなく、顧客の業務課題や法規制を正確に把握した上での提案が求められるため、一般的な営業代行会社では対応が難しいことがあります。
また、「御社だから信頼して発注したい」といった関係性が求められる業種では、第三者の営業担当が介入することでブランドの価値が損なわれてしまうリスクもあるのです。
このような場合には、外部委託ではなく、社内で営業体制を構築・強化する方が長期的には成果につながる可能性が高いと言えるでしょう。
営業代行で失敗しないための業者選びポイント
営業代行を活用して成果を出すためには、「どの業者を選ぶか」が非常に重要です。ここでは、失敗を避けるために押さえておきたい3つの選定ポイントをご紹介します。
契約条件と料金体系の明確化
まず最初に確認すべきなのは、契約内容と料金体系の透明性です。営業代行には大きく分けて「固定報酬型」「成果報酬型」「ハイブリッド型(基本料金+成果報酬)」の3つの料金形態があります。
- 固定報酬型:月額料金が一定で、稼働時間や件数にかかわらず支払う必要がある。
- 成果報酬型:アポイント獲得や成約数に応じて報酬を支払う。
- ハイブリッド型:一定の基本料金に加え、成果に応じて追加報酬が発生。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の予算や営業目標に応じて最適な形態を選ぶことが大切です。たとえば、「成果が出るまでは支払いを抑えたい」という場合には成果報酬型が合っていますが、「リスクを抑えつつ戦略的に伴走してもらいたい」という場合にはハイブリッド型がおすすめです。
また、契約書の中に記載されている成果定義(例:有効なアポイントとは何か)や、解約条件、途中終了時の精算ルールなども明確にしておく必要があります。不明瞭な点があると、後々トラブルになることもありますので注意しましょう。
業界知識・過去実績のチェック
営業代行会社を選ぶ際には、自社と同じような業界・ターゲット層での実績があるかどうかを必ず確認しましょう。代行業者の中には、得意な業界が明確に分かれているところもあります。
たとえば、BtoBに強い会社、BtoC商材に特化した会社、SaaSやIT系に豊富なノウハウを持つ会社など、それぞれ専門分野があります。そのため、単に「営業が得意」というだけではなく、「どのような業界で、どのような成果を上げてきたのか」という実績をヒアリングすることが不可欠です。
ホームページの導入事例や口コミ、評判だけではなく、初回相談時に過去のクライアント業種や成果事例を尋ねるのがよいでしょう。また、できれば同業他社の導入実績がある業者を選ぶことで、商材の理解度やターゲット戦略のミスマッチを防ぐことができます。
進捗管理・レポーティング体制の確認
営業代行を利用する際にありがちなトラブルが、「営業活動の状況が全く見えない」「進捗報告がない」といった不透明さです。これを防ぐためには、レポーティング体制やコミュニケーションの頻度を事前に確認しておくことが重要です。
たとえば、以下のような点を確認しておきましょう。
- 営業進捗は週次または月次で報告されるか?
- 使用するレポートフォーマットはどういったものか?
- 顧客の反応やネガティブな声も共有されるか?
- チャットやZoomなどで定例MTGが組まれているか?
営業代行会社との連携がうまくいかないと、結果的に費用だけがかかり、成果につながらないことになりかねません。密な情報共有と定期的なフィードバック体制がある会社を選びましょう。
営業代行導入前のチェックリスト
営業代行を導入する前に、いくつかの重要な確認項目があります。これを疎かにすると、代行業者との連携がうまくいかず、期待した成果を得ることが難しくなります。以下のチェックリストをもとに、準備状況を見直してみましょう。
目的とKPIは明確か?
営業代行を導入する目的が「とにかく売上を上げたい」という曖昧なものになっていないでしょうか?目的が不明確なまま依頼してしまうと、業者との目標共有が不十分になり、効果検証ができないまま終わってしまう可能性があります。
たとえば以下のような目的を明確にすることが大切です。
- 月間○件の新規アポイントを取得したい
- ○業種の新規リードを開拓したい
- 導入実績を増やして信頼性を高めたい
さらに、これらの目的に対してKPI(重要業績評価指標)を設定することで、成果の可視化がしやすくなります。例としては「架電数」「アポ獲得数」「商談化率」「成約率」など、各フェーズで数値目標を明確にしておきましょう。
社内との役割分担は適切か?
営業代行を導入する際には、どこまでを外部に委託し、どこからを社内で担当するのかという役割分担を明確にする必要があります。
例えば、以下のような分担が考えられます。
- 架電・アポ取得 → 営業代行
- 商談・クロージング → 自社営業担当
- 見込み顧客のリスト作成 → 自社マーケティング部門
このように役割を切り分けることで、無駄な重複や抜け漏れを防ぐことができます。特に見落とされがちなのが、リード管理やアフターフォローの領域です。アポ取得後の顧客対応が不十分だと、せっかくの見込み顧客も成約に結びつきません。
導入前に「誰が・何を・いつまでに」対応するのかを整理し、社内外の連携体制を整えておきましょう。
情報管理や機密保持の準備は整っているか?
営業代行業者に対しては、企業の大切な顧客情報や営業戦略を共有する必要があります。そのため、事前に情報セキュリティ対策や契約関連の整備を行っておくことが不可欠です。
具体的には、以下のような対応が必要です。
- 秘密保持契約(NDA)の締結
- 顧客リスト・営業資料の共有範囲の明確化
- セキュリティ体制(端末管理、クラウド共有など)の確認
- 顧客情報の取り扱いルールの事前説明
こうした準備が整っていないと、情報漏洩やコンプライアンス違反のリスクを抱えることになります。トラブルを未然に防ぐためにも、導入前の段階で必要なルールや契約を明確にしておきましょう。
営業代行を成功に導く3つの活用戦略
営業代行を単なる「外注」として活用するのではなく、パートナーとして共に成果を追い求める体制を築くことが重要です。以下の3つの戦略を意識することで、営業代行をより効果的に活用することができます。
部分委託とノウハウの社内共有
営業代行を活用する際には、業務のすべてを丸投げするのではなく、「部分的な委託」にとどめるのが理想です。たとえば、リスト作成やアポ取得など、社内で対応しきれない部分だけを任せる形にすると、社内にも営業の知見を残すことができます。
また、代行業者がどのように成果を出しているのか、その営業スクリプトや手法を社内にフィードバックしてもらうことで、ナレッジの蓄積にもつながります。これにより、自社の営業力も同時に高めることができ、将来的には自走できる体制を築くことが可能になります。
PDCAによる継続的な改善体制
営業代行に任せっきりにならず、定期的なレポートやミーティングを通じてPDCAを回していくことが成功へのカギとなります。
- Plan(計画):ターゲット選定、スクリプトの見直し
- Do(実行):アプローチ活動の実施
- Check(確認):結果分析とボトルネックの特定
- Act(改善):改善策の実施と再計画
このPDCAサイクルを代行業者と共有しながら運用することで、活動の質を徐々に高めることができ、最終的には高い成果につながります。代行業者との関係を「使う/使われる」ではなく、「共に成果を追うパートナーシップ」として考えることが大切です。
「外注」ではなく「戦略パートナー」として関係構築
営業代行を「単なる外部委託先」として見るのではなく、「自社の営業戦略を支えるパートナー」として位置づけることで、双方にとってメリットのある関係を築くことができます。
たとえば、自社のミッションや提供価値、顧客との接点における重要な指針などをしっかりと共有し、代行業者が自社の一員のように活動できるようにサポートすることが重要です。
また、成果が出た際には感謝を伝えるなど、信頼関係の構築にも意識を向けましょう。こうした姿勢が、代行業者のモチベーション向上や業務品質の向上にも直結し、結果的により良い成果を生む土台となります。
営業代行の料金体系の全体像
営業代行を導入するにあたって、最も重要な判断材料のひとつが「料金体系」です。営業代行は安価なサービスではなく、費用対効果が成果に直結するため、料金の内訳や報酬形態をしっかり理解しておく必要があります。
固定報酬・成果報酬・ハイブリッドの違い
営業代行の料金体系には大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを以下にまとめます。
① 固定報酬型 月額で一定の料金を支払う契約形式です。業務時間やアプローチ数にかかわらず、一定額を支払うため、コストが見通しやすいというメリットがあります。
メリット:
- 毎月の予算が安定する
- アポイント獲得の件数に左右されず契約が続けやすい
デメリット:
- 成果が出なかった場合でも費用が発生する
- 成果を重視しない業者の場合、モチベーションが低くなる懸念あり
② 成果報酬型 アポ取得数や商談化数など、成果に応じて料金が発生する形式です。初期コストを抑えたい場合や、成果が出なければ支払いがないためリスクを軽減できます。
メリット:
- 成果が出ない場合、費用が発生しない安心感
- 代行業者が成果にコミットしやすくなる
デメリット:
- 高単価になりやすい(1件あたりのアポ報酬が3~5万円など)
- 質より量を優先したアポが増える傾向も
③ ハイブリッド型 基本料金(固定)+成果に応じた報酬という組み合わせです。ある程度の安定収益を確保しつつ、成果にインセンティブを与える形になります。
メリット:
- 双方のバランスをとった最も現実的なプラン
- 成果へのモチベーションと継続的な支援が期待できる
デメリット:
- 条件や費用構成が複雑になりやすい
- 初期費用が高く感じるケースもある
見落としがちな追加費用と契約の落とし穴
営業代行の契約では、基本料金以外にも思わぬコストが発生することがあります。見積もり時には提示されない項目が、後から「追加費用」として請求されるケースもあるため注意が必要です。
以下のような費用項目に事前に目を通しておきましょう。
- 初期費用(リスト作成費、戦略設計費など)
- ツール利用料(CRM・架電ツールなどのライセンス費)
- 月次レポートや打ち合わせ対応の追加費
- 交通費、電話代などの実費精算
- アポの質に関わる「条件付き成果報酬」(例:◯◯役職以上限定)
また、最低契約期間や中途解約時の違約金についても必ずチェックしてください。契約書の文言が曖昧な場合は、事前に営業担当者に口頭で確認し、できれば文面でも明文化しておくことをおすすめします。
営業代行の市場動向と将来性
営業代行はかつて「短期的な営業補完」としてのイメージが強いサービスでしたが、近年では事業戦略の中核としての位置づけが強まりつつあります。その背景には、日本全体の人材不足、営業手法の多様化、そしてテクノロジーの進化があります。
人手不足とアウトソーシング需要の高まり
少子高齢化が進む中で、営業人材の確保は多くの企業にとって深刻な課題となっています。特に東京では、営業職の採用難易度が年々高まり、未経験人材の育成にも多大なコストがかかる状況です。
このような背景から、短期的にリソースを補完できる「営業代行」の需要が急速に高まっています。営業を社内でゼロから育てるのではなく、即戦力となる外部の専門人材を活用することで、事業スピードを落とすことなく成長を目指す企業が増えているのです。
また、在宅勤務やリモートワークの普及により、従来の「常駐型営業」から「分業型・成果型」へと営業スタイルがシフトしている点も、営業代行の導入を後押しする要因となっています。
インサイドセールスや自動化との融合
従来の営業代行は、テレアポ中心のアウトバウンド業務が主流でした。しかし現在では、マーケティングオートメーション(MA)ツールやインサイドセールスとの組み合わせによる「高度な分業化」が進んでいます。
具体的には以下のような進化が見られます。
- MAで育成したリードに対し、インサイドセールス(代行)がアポ取り
- CRMで顧客情報を一元管理し、営業活動を可視化
- チャットやメールマーケティングなどを含む多チャネル連携
- AIによる商談履歴の自動分析・優先順位付け
これにより、営業活動の精度と効率が格段に高まり、「ただ電話をかけるだけの代行」から「戦略的に成果を出すパートナー」へと営業代行の役割が進化しています。
今後は、SaaS系企業を中心に「営業代行×テクノロジー」を軸とした新しい形のアウトソーシング需要がさらに高まると予測されています。
【実例紹介】営業代行・フリーランス活用の成功事例
営業代行やフリーランス営業は、「やめとけ」といった否定的な声がある一方で、正しい使い方をすれば大きな成果を上げている企業も少なくありません。ここでは、実際に成功を収めた事例をご紹介し、どのように活用すれば自社の成長に繋がるのかを解説します。
中小製造業が成果報酬型代行で売上3倍
東京都内のある金属加工メーカーでは、営業部門の人員不足が深刻化しており、新規開拓が滞っていました。社長が営業に出ることも多く、既存顧客の対応に手一杯な状況だったため、営業代行会社にテレアポとアポ取得を委託することにしました。
採用したのは「成果報酬型」の営業代行で、業界経験が豊富な担当者が付き、ターゲットリストの選定からスクリプト作成、アポ設定までを一括対応。開始3ヶ月目からは月10件以上のアポが安定して入り、6ヶ月で成約件数が従来の約3倍に増加しました。
この企業では、「成果の定義」を明確に契約書に盛り込み、週次のレポートとフィードバック会議を実施することでPDCAを回し続けたことが成功のカギでした。
IT企業がフリーランス営業で展示会アポ数倍増
都内のSaaS系スタートアップ企業では、展示会に出展してもアポ獲得が思うように進まず、商談数が伸び悩んでいました。そこで、展示会営業を専門に請け負うフリーランス営業パーソンに依頼することに。
フリーランスの営業担当者は、過去に展示会運営やリード獲得を多数手がけていた経験者で、ブースでの話し方やアンケート設計、導線づくりまでを設計。さらに、展示会後のフォローコールも担当し、質の高いアポを短期間で多数創出しました。
結果として、過去の展示会に比べて約2.5倍のアポ数を獲得し、その後の成約率も30%以上に改善。自社営業チームに対しても、展示会営業のノウハウをレクチャーしてくれたため、社内スキルの向上にも繋がりました。
このケースでは、「一時的な委託」で終わらず、社内の教育と営業戦略にまで貢献できた点が高く評価されています。
営業代行を卒業し自社営業に移行する方法
営業代行を一定期間活用したあと、「そろそろ自社で営業を強化していきたい」と考える企業も少なくありません。外部委託から内製化へとスムーズに移行するためには、段階的なステップと体制づくりが不可欠です。
段階的な移行ステップと教育体制の構築
いきなり営業代行をすべて解約して自社営業に切り替えるのはリスクが高いため、段階的な移行を行うのが現実的です。以下は、スムーズに移行するための一連のステップです。
- 営業代行のアプローチ手法やスクリプトをドキュメント化
- 社内営業担当者と代行業者との同行営業やロールプレイングを実施
- 社内でトライアル期間を設けて営業活動を実施(週数件など)
- 成果指標を元に徐々に稼働を移行し、代行業務を縮小
- 社内営業に完全移行し、必要に応じて定期コンサルを受ける
このように、外部ノウハウを内製化するプロセスを設計することで、成果を出しながら自社の営業力も高めていくことができます。
自社営業力を育てる体制づくり
営業代行に依存せず、自社内で継続的に営業成果を出すには、「人」「仕組み」「評価」の3つを整えることが不可欠です。
1. 営業人材の採用・育成: 営業適性のある人材を採用し、体系的な教育プログラムを構築します。外部講師による研修や、OJT・ロープレの導入も有効です。
2. 営業プロセスの標準化: SFAやCRMツールを活用し、営業活動の進捗や顧客データを見える化します。スクリプト、商談資料、FAQなども統一して、属人化を防ぐことが大切です。
3. 成果の評価・改善: KPIベースの評価制度を導入し、成果を数値で確認できるようにします。また、月次の営業会議などでフィードバックを行い、PDCAを常に回す文化を定着させましょう。
これらの体制が整えば、営業代行を卒業しても、自社の中に「継続的に売上を創出できる仕組み」を築くことが可能となります。
まとめ:「営業代行やめとけ」は誤解?成功するための選択とは
営業代行は「やめとけ」といった否定的な意見が検索される一方で、実際には正しく使えば大きな効果を発揮するビジネスツールでもあります。重要なのは、「目的に合った活用方法」と「信頼できるパートナー選び」、そして「自社に最適な体制の見極め」です。
良い業者との出会いが成功の鍵
どれだけ営業代行の仕組みが優れていても、依頼先の代行業者の質が低ければ、成果は望めません。営業経験の豊富さだけでなく、報告体制や業界知識、担当者の人柄なども含めて、自社との相性を重視することが不可欠です。
また、契約前には「成果の定義」や「成功報酬の仕組み」「情報管理体制」など、あいまいにしがちな部分までしっかり確認し、トラブルを未然に防ぐ工夫も必要です。
最適な営業体制は企業によって異なる
営業代行が最適な企業もあれば、自社営業のほうが向いているケースもあります。さらに最近では、フリーランス営業やインサイドセールスとのハイブリッド運用など、多様な選択肢が存在します。
大切なのは、「今、自社にどのようなリソースがあり、どのような成果を求めているのか」を正確に把握した上で、柔軟に営業戦略を組み立てることです。固定観念にとらわれず、効果的なリソース配分を実現することが、事業成長のカギを握るのです。
営業代行を「短期的な応急処置」ではなく、「戦略的パートナー」として活用する姿勢が、結果的に自社の営業力を大きく育てる第一歩となるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 営業代行と販売代理店の違いは何ですか?
営業代行は主に「営業活動の実行」を受託するサービスであり、契約や請求業務は自社で行います。一方、販売代理店は商品の仕入れや契約も含めた代理販売を行う点が大きな違いです。
Q2. 東京でおすすめの営業代行会社を選ぶには?
「業界特化の実績」「成果報酬かどうか」「レポート体制があるか」などの要素を基準に選ぶのが良いでしょう。また、東京都内にはSaaS、医療、製造などに強みを持つ会社が多数あるため、商材との相性も重視してください。
Q3. 営業代行を導入するのに向かない業種はありますか?
高度な専門知識を要する士業(弁護士・税理士等)や、ブランド力が重視される高級商品などは、営業代行がうまく機能しないことがあります。このような場合は、自社営業またはハイブリッド体制の構築が推奨されます。
Q4. 成果報酬型と固定報酬型、どちらがおすすめですか?
初期リスクを抑えたい場合は成果報酬型、継続的に営業活動を強化したい場合は固定もしくはハイブリッド型がおすすめです。企業のフェーズや予算に応じて選択することが大切です。
Q5. 営業代行を使いながら自社営業力も強化できますか?
はい、可能です。部分的な委託を活用しながら営業代行のノウハウを社内に還元することで、自社の営業スキルも同時に育成することができます。定期的な同行営業や社内教育との連携がカギとなります。
おすすめの営業代行サービス
「受注アシストサービス」は、リードの徹底フォローと商談後のクロージングアシストに特化した『営業社員代行』です。 営業担当者の負担を減らし、本来の商談活動に集中できる環境を作ることで、成約率のアップを実現します。



